日本人の食生活・栄養の問題点とは?② 主食・主菜・副菜を組合わせた食事の実践方法
前回は、日本人の食生活・栄養の3つの問題点を解説しました。今回は、それぞれをクリアするための対策や工夫について解説します!
- ▽日本人の食生活・栄養の問題点(全5回)
- 1.健康日本21(第2次)
- 2.主食・主菜・副菜の組合わせ
- 3.食塩についての対策や工夫
- 4.野菜・果物の正しい摂り方
- 5.野菜の食べ方をもっと楽しもう!

1日2回以上!主食・主菜・副菜をしっかり摂取

人は食べなければ生きることができません。
食べることによって人は栄養素などの成分を体内に取り込み、そこからエネルギーを産み出し、体の組織を作るなどして生命を保っています。
なぜ主食・主菜・副菜を組合わせた食事が大切なのかというと、それぞれに使われる代表的な食材には、異なる栄養素が含まれているからなのです。
| 主食 | ごはん、パン、麺などの「炭水化物(糖質)」を含む食材 |
|---|---|
| 主菜 | 肉、魚、卵、大豆・豆製品などの「タンパク質」を含む食材 |
| 副菜 | 野菜、いも類、海藻などの「ビタミン・ミネラル」を含む食品 |
◆7大栄養素について詳しい記事はこちら
◆栄養バランスの良い食事方法に関する記事はこちら
代謝が活発な若年層や自分自身の健康状態に無頓着な方は、栄養バランスの乱れからの体調の変化に気が付かないことが多いようですが、生活習慣病などは症状が表れてから気が付いたのでは手遅れであるケースも少なくありません。
食生活に問題がある、と気付いた瞬間から、正しい食生活の実践を心がけてみましょう!
食事の組立てが簡単になる!「弁当箱」の活用

最近では海外からも注目されている、日本の食文化の一つである弁当。
弁当を入れる容器である弁当箱は、食事のコントロールの際にとても便利なアイテムで、主食・主菜・副菜を組合わせた食事の実践に効果的です。
お弁当箱の容量はカロリーと相関があるという説があり、例えば500mlの弁当箱を使って弁当を作ると、だいたい500kcal前後のものが完成するといわれています。
一日に必要な自分自身のエネルギー量を算出して1/3にしてみると、一食当たりどの程度のエネルギーを摂取できるのかが分かります。
◆一日に必要なエネルギー量の計算方法
※一食当たりのエネルギー量の配分には諸説がありますが、ここでは分かりやすく1/3を採用しています。
まずは一食からでも実践してみよう
| 主食 (全体の半分のスペース) |
主菜 (全体の1/6のスペース) ※1~2品程度 |
|---|---|
| 副菜 (全体の1/3のスペース) ※2品程度 |
自分のエネルギー量に見合った弁当箱を見つけたら、上記の図のような配分で詰めていきます。
炭水化物(糖質)はおよそ半分程度のスペースを用います。そして、残りの半分のスペースに主菜と副菜を詰めていきます。
スペースが決まっていると詰められる量も自ずと限られてきますから、どのくらい食べれば良いか、といった基準が自分の中で生まれます。
まずは一食弁当箱を活用してみることで、弁当箱を使わずともそれぞれの配分が体感できますので、健康的な食生活を実践してみたい方はぜひ行ってみてください。
最近ではおしゃれなデザインや形の弁当箱が多数販売されていますので、お気に入りの一つを探してみましょう。
洋服をコーディネートするようにお弁当箱やクロスを選ぶのも楽しいですよ!
今回は1つ目の問題点として、主食・主菜・副菜を組合わせた食事の実践について解説しました。次回は食塩の摂取についてを解説します!
- ▽日本人の食生活・栄養の問題点(全5回)
- 1.健康日本21(第2次)
- 2.主食・主菜・副菜の組合わせ
- 3.食塩についての対策や工夫
- 4.野菜・果物の正しい摂り方
- 5.野菜の食べ方をもっと楽しもう!



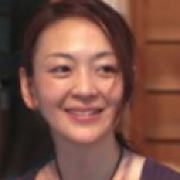 松下 和代
松下 和代
 永吉 峰子
永吉 峰子





