冬至にかぼちゃを食べる~由来と2つの理由を解説!
「冬至にかぼちゃを食べる」これは古くから日本の習慣です。でも、なぜ習慣があるのかはあまり知られていませんよね。そこで冬至のかぼちゃの由来や理由、そしてかぼちゃの栄養素やおすすめの調理法についてもお伝えします。

冬至ってどんな日?
1年で最も昼間が短い日
冬至は北半球の1年で最も日照時間が短くなる日です。毎年12月22日前後で、2016年は12月21日です。
これから昼間が長くなる、縁起がよい日
冬至は節分を基準にして1年を24等分する「二十四節気」の1つ。その中でも冬至は、この日を境に日が長くなる、つまり運気が上昇する日とされています。このように冬が終わり日の長い時期がやってくることを「一陽来復」といい、とても縁起の良い日とされています。
冬至にかぼちゃを食べた理由2つ
1. 縁起の良い日は「運盛り」していた
冬至など縁起の良い日に「ん」がつく食べ物を食べ運気を上げる「運盛(うんも)り」という習慣があります。かぼちゃは南瓜(なんきん)とも言い、古くから縁起のよい食べ物とされてきました。
かぼちゃの他にも「ん」がつく人参やこんにゃくを食べたり、縁起の良い赤色のあずきとかぼちゃを煮た「いとこ煮」を食べたりする地域もあります。
2. 貴重なビタミン源を食べて冬を乗り切る!
昔は秋が終わると新鮮な野菜がとれず、冬は夏に収穫した野菜を貯蔵して食べていました。その野菜の中でも、ビタミン豊富なかぼちゃは貴重な栄養源。
昔は暖房も不十分で、食料も少なかったので体調を崩すと、そのまま亡くなってしまうこともありました。その為、冬至のかぼちゃで栄養を摂取することはとても大切な事だったのです。
かぼちゃの栄養素の秘密
かぼちゃにはビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、カリウムなど、たくさんのビタミンやミネラルが含まれており、風邪予防や美肌効果、疲れ防止などの効果が期待できます。
関連リンク: ビタミンA | ビタミンC | ビタミンE | カリウム
風邪やインフルエンザの予防が期待できる!
ビタミンAには免疫を強化する働きがあり、ビタミンCは寒さなどのストレスから体を守る働きがあります。またビタミンEは血流をよくする働きがあります。
その為、かぼちゃを食べることで体が温まり、殺菌やウイルスに強くなって、風邪やインフルエンザの予防が期待できます。昔の人々は体験的にこのことを知っていたのかもしれませんね。
美肌効果も期待!
ビタミンAには粘膜を作るのを助ける働きがあり、ビタミンEには血行をよくする働きがあります。またビタミンCにはシミ予防の働きがあります。
その為、かぼちゃを食べることで肌に栄養が行きわたってシミもできにくくなり、美肌効果が期待できます。
年末の疲れた体にもおすすめ!
かぼちゃに含まれるビタミンB群には、糖質、脂質、たんぱく質の代謝を助ける働きがあります。その為ビタミンB群を摂取することで、代謝がスムーズになり疲れにくい体にすることができます。
また、カリウムには余計な水分を排出する効果があります。余計な水分が貯まるとむくみにつながり、冷えや疲労感につながってしまいます。その為カリウムを摂ることで体をすっきりさせることが期待できます。
関連リンク: 糖質 | 脂質 | たんぱく質 | カリウム
かぼちゃにおすすめの調理法とは?
水に溶けたビタミン成分を逃さず摂取!
かぼちゃのビタミンの中、ビタミンCとB群は水に溶けやすいビタミンです。その為、煮込んだり、スープにしたりして、汁ごと食べるのがおすすめです。また焼き・蒸しもビタミンの損出が少なくおすすめです。
油と一緒にとってビタミン吸収アップ!
ビタミンAとビタミンEは油に溶けやすいビタミンなので、油と一緒に食べると吸収率がアップします。ドレッシングや炒めものなど、油と一緒に調理するとよいでしょう。
おすすめレシピ「かぼちゃとベーコンのチーズ焼」
かぼちゃに合わせる食材は、たんぱく源となる肉やカルシウム豊富な乳製品がおすすめ。ビタミン豊富なかぼちゃと摂ることでバランスが整いますし、肉や乳製品の油分でビタミンの吸収がよくなります。
【材料】(2人前)
・かぼちゃ1/4カット
・ベーコン 2枚
・とろけるチーズ 適量
【作り方】
① かぼちゃは1cm程度の薄切りにし、耐熱皿に入れてラップをかけて5分ほど加熱する。(楊枝がさせる柔らかさになるまで加熱する)
② 耐熱皿に油(分量外)を薄く敷き、かぼちゃ→カットしたベーコン→チーズの順に重ね、もう1度この順番で加熱する。
③ オーブントースターで10分~15分焼く。チーズが溶けたら出来上がり。



 高木 沙織
高木 沙織
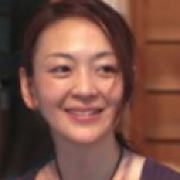 松下 和代
松下 和代



