糖質制限ダイエットってどうなの?正しい仕組みと5つの注意点を理解しよう!【後編】
前編では、ダイエットの基本と糖質制限の仕組みについてお伝えしましたが、後編では、糖質制限ダイエットをする上での、5つの注意点についてお伝えします。
過度で無茶な糖質制限は、ダイエットのリバウンドに繋がったり、身体の異常につながりますので、ぜひ正しい仕組みと注意点を理解したいただければと思います。

「糖質制限ダイエット」は良いの?
それでは、この「糖質制限」で体が「飢餓状態」であることは、本当に有効で画期的なダイエット方法なのでしょうか?
厚生労働省より推奨されている炭水化物の摂取量は、1日の全体の食事より50~70%と言われています。そのため「糖質制限ダイエット」には、その大切な糖質の役割を妨げてしまう恐れがあることも頭においてください。
関連リンク: 炭水化物(糖質)
「糖質制限ダイエット」を行う5つの注意点
「糖質制限ダイエット」を行う時には、注意してほしいポイントを5つまとめました。このことを頭に入れてダイエットを行ってください。
1.脳で使われるエネルギーは「ブドウ糖」からのものしか利用できません。
体のエネルギーはそもそもどの場所も同じように、同じエネルギーを作っているわけではありません。脳は血液中の栄養素の中から、脳関門と言われる場所でブドウ糖のみをエネルギー栄養素として通します。そのためこの糖質制限ダイエットでは、脳へのエネルギー不足による集中力の低下やイライラ、長期的には脳梗塞へつながる恐れがあるのです。
2.実行してすぐに体重が減る見せかけの変化に惑わされないでください。
糖質を制限すると、肝臓で使われるグリコーゲンは、一緒に水分も多く使われているため体の水分量が減っていきます。そのため、1キロ~2キロ前後の体重の変化はすぐに現れます。
通常、筋肉は脂肪に比べて重さがあるため同じ体重では、筋肉質の方の方が脂肪のある方より痩せて見えるのはそのためです。脂肪を筋肉に変えていくダイエットでは、そう簡単に体重は変わりません。
リバウンドせずに、正しいダイエット方法では、筋肉量を増やし、基礎代謝量をあげていく形が理想です。まずダイエットを行う際に、体重だけでなくご自身の体脂肪や筋肉量を意識していきましょう。
3.糖質不足によって起こるケトン体に注意しましょう。
ブドウ糖が不足すると、脂質を燃焼してエネルギー源とするため、その代謝産物として「ケトン体」が作られます。「ケトン体」は、体に多くなると体液が酸性に傾き、悪心や嘔吐、ひどい場合には昏睡状態などを引き起こします。また長期的に、疲れやすい体質になっていきます。
4.糖質を摂らない代わりで起こる栄養バランスの不足に気を付けましょう。
糖質を減らした部分を「たんぱく質」や「脂質」で摂取量が増やすことにより、栄養バランスが乱れます。そして「たんぱく質」を過剰にとりエネルギーとすると、腎臓や肝臓に負担がかかります。
さらに「たんぱく質」と一緒に取り込みやすい過剰な「脂質」は動脈硬化を促進させて、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める恐れがあると指摘されています。また、偏ったバランスの食生活から起こる「たんぱく質」の低下から筋肉量が減ることで、骨粗鬆症(こつそそうしょう)の心配も生じてきます。
関連リンク: タンパク質 | 脂質
5.食物繊維の不足に注意しましょう。
「糖質」のもとである「炭水化物」には、穀物や芋類・果物などから得られる食物繊維や人体に不可欠な栄養素が多く含まれています。そのため、過剰な「糖質制限ダイエット」では、食物繊維の不足によって起こる便秘などの不調が生じます。
糖質を減らしたダイエットを行う場合には、補う栄養素として食物繊維を積極的にとっていくようにしましょう。
関連リンク: 食物繊維 | 炭水化物(糖質)
おわりに
さてここまで、長くお伝えしましたが「糖質制限ダイエット」を行う際には、まず専門の医師や管理栄養士さんのお話を伺ってきちんとした指導の上で、実践してください。
特に、糖尿病などの持病のある方は、安易に行わないように注意して健康な体作りを目指していきましょう。

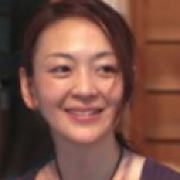

 ライフミール栄養士
ライフミール栄養士


 仲里あやね
仲里あやね

