今流行りの「ヴィーガン」は「ベジタリアン」「マクロビオティック」と何が違うの?【前半】
最近よく「ヴィーガン」という言葉を耳にします。ハリウッドセレブの間でも噂になり、日本でもこうしたスタイルを持った人も増え、専用のレストランやショップができてきました。
しかし、この「ヴィーガン」ですが、何となく「野菜を食べる人たち」とイメージができるのですが、「ベジタリアン」や「マクロビオティック」とは何が違うのでしょうか?
今回は、この三つの食の生活様式と栄養面についてまとめてみました。

「ヴィーガン」のはじまり
まず「ヴィーガン」とは、1944年イギリスでドナルド・ワトソン(英ヴィーガン協会の共同設立者)によって作られた「人間は動物を搾取することなく生きるべきだという主義」をもとにVeg (etari) anを短縮してつくられた造語です。
日本語では、「純粋菜食者・完全菜食主義者」を指します。
それまであった「ベジタリアン」と違い、食事では乳製品、蜂蜜等も含む動物性の食品を一切摂らず、生活でも革製品等食用以外の動物の利用も避けているため、かなりストイックなライフスタイルと言えるでしょう。
多様化されるフードライフスタイル(食の生活様式)
このかなり厳しい制限のある「ヴィーガン」の中でも、少し縛りをなくして生活をしている方々もいます。その形は実に多種多様で、食の生活様式(フードライフスタイル)にも違いが見られます。
食の生活様式(フードライフスタイル)とその名称
ダイエタリー・ヴィーガン
完全に菜食主義ではあっても動物性の製品は避けない
ラクト・ベジタリアン
動物、魚介類、卵は食べず、乳製品、蜂蜜は食べる
オボ・ベジタリアン
動物、魚介類、乳製品は食べず、卵、蜂蜜は食べる
ラクト・オボ・ベジタリアン
動物、魚介類は食べず、乳製品・卵・蜂蜜は食べる
オリエンタル・ベジタリアン
精進料理を含む仏教的な思想から、殺生を好まず、食物でも香りの強いにんにく、にら、らっきょう、ねぎなどの(五葷ごくん)を食べない
フルータリアン
ヴィーガンとは少しだけ思想が異なり "収穫しても植物自体を殺さない" 考えに基づいて植物を選んで食べる
ポロ・ピスコタリアン
哺乳類からの肉を避けるため、魚も哺乳類は食べない
この他、国や宗教、健康や道徳の思想、生活様式などの違いから、多種多様に食の方法も変化し、それぞれに呼び方が異なってきます。
「ヴィーガン」より古い歴史の「ベジタリアン」
「菜食主義」の思想は古く紀元前のギリシャから始まります。オルペウス教の輪廻(りんね)思想によって「動物と人間は同等である」として菜食を実践していました。
当時、菜食主義者は古代ギリシャの哲学者のピュタゴラスにちなんで「ピュタゴリアン」と呼ばれていました。これが、野菜のベジタブルと語呂の良い「ベジタリアン」に変わったとも言われています。
さらに仏教でも、古くより殺生を避ける目的から「菜食主義」を行っていた時代がありました。このように人間が、肉食を避ける思想は古くからありました。
そして日本では、英語の「Vegetable」に人を表す「tarian」の語尾をつけたものとして「ヴィーガン」より以前に「ベジタリアン」(菜食主義者)として浸透していきました。
近年、この「ヴィーガン」と言った言葉が「菜食主義」をより厳しくしたライフスタイルとして、捉えるようになってきました。
各国の「ベジタリアン協会」では「ベジタリアン」の定義として「菜食だけ、または菜食に加えて本人の選択により卵と乳製品を摂る人々をベジタリアン」としています。
日本では「ベジタリアン」と「ヴィーガン」の違いがわかりづらくなっていますが、どちらも「野菜や穀物を中心に食生活を行っている」点では共通しています。
マクロビオティックは日本が発祥
「マクロビオティック」と聞いた時、欧米からのものと考えがちですが、実は明治26年思想家の桜沢如一(さくらざわ・ゆきかず)による食の思想から広まったものと言われています。
そもそもの語源は、古代ギリシャ語「マクロビオス」によるものと言われていますが、「マクロ(大きい・長い)」「ビオ(生命)」「ティック(術・学)」の三つの語源をつなげ「人が長く生きるため宇宙レベルの大きな視野で生命を見る理論」として考えられ広めたのが桜沢になります。
この考えの基本には、身土不二・一物全体・陰陽調和の3つがあります。
身土不二(しんどふじ)
「身土不二」と言われる身体と環境は切り離せないものとし、無農薬・自然農法の穀物や野菜を中心に、地産地消で旬のものを食べる思想。
一物全体(いちぶつぜんたい)
「食材を丸ごと無駄なく食べる」考え(例えば、米なら玄米、野菜であれば、皮も根も種も丸ごと食べる)思想
陰陽調和(おんみょうちょうわ)
東洋の伝統的な世界観「陰陽調和」に基づき、体を締める食品は「陽性」緩めるものは「陰性」、体を温めるものは「陽性」、冷やすものは「陰性」といったような分け方をした思想が根本になります。
暑い季節には陰性の食べ物、寒い季節には陽性の食べ物が向くなど、陰陽のバランスを整え「調和が大切」という考え方をもとにしています。
桜沢の活動は、その後1960年に弟子の久司道夫らとともに「禅・マクロビオティック」と唱えて渡米し、普及させていき世界に広がり今の形ができあがりました。
「マクロビオティック」は「ヴィーガン」のような「完全な菜食主義」とは異なり、場合によっては肉や魚も食べます。食事療法とは違い、生活そのものを改善するような平和運動を伴った哲学的な要素が根底にあるのが大きな特徴です。
後半は、野菜中心の食生活を送った場合のメリット&デメリットを栄養士視点でお伝えいたします!

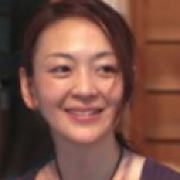

 高木 沙織
高木 沙織


 ライフミール栄養士
ライフミール栄養士

